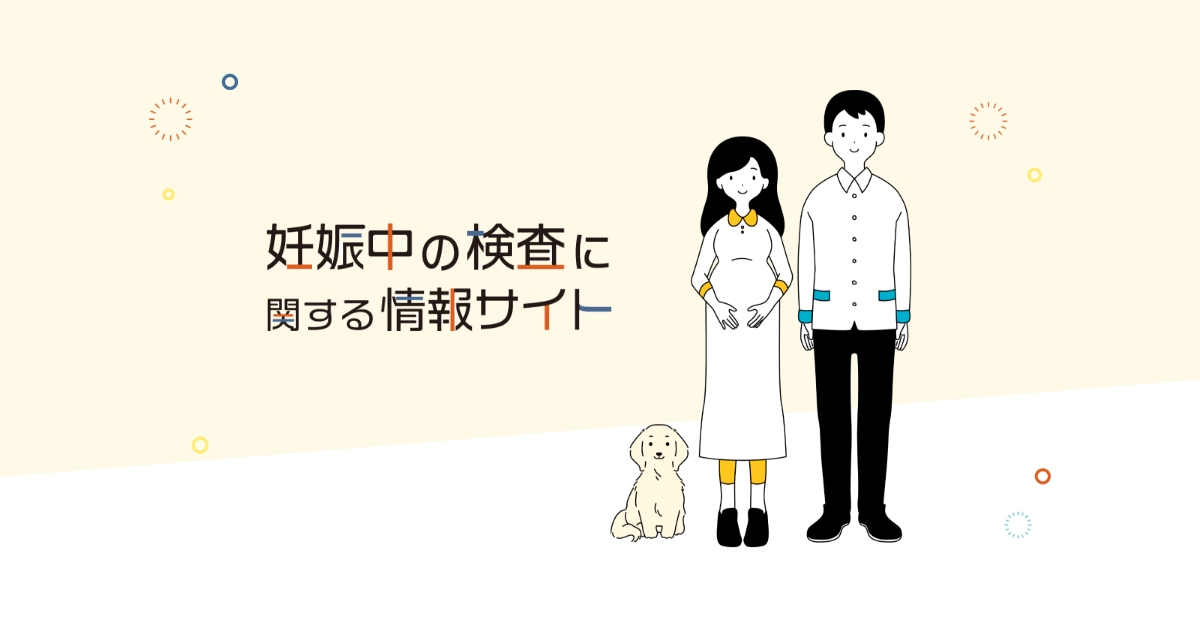つい先日、久しぶりに出生前検査認証制度運営委員会のウェブサイトにアクセスしたのですが、1月に一般の方向けの情報が公開されるなど徐々に内容が充実してきているようですね。
実は今年3月に、令和4年度出生前検査認証制度等広報啓発事業(厚生労働省補助事業)によって「妊娠中の検査に関する情報サイト」が作成され、公開されています。
わたしはこのサイトの作成に協力したのですが、検査についての説明を作成するにあたり、認証制度運営委員会(以下、“委員会”と記載します)のサイト内の記載との整合性の問題があって、難渋しました。
まあ、わたしの“こだわり”みたいな部分があって、取りまとめをする人にはご苦労をおかけしたのではないかとも思いますが、特にこだわったのは羊水検査や絨毛検査(いわゆる“侵襲的検査”とされるもの)のリスクに関する記載です。
そもそも出生前検査として認識されている各種検査について、「確定的検査」「非確定的検査」という分け方をすることについても以前より違和感があり、この分け方にしてほしくないと主張して言葉を変えてもらったのですが、一緒に作業をした先生方には、私の意見をよく理解していただけました。そんな中で、侵襲的検査にはいったいどのぐらいのリスクがあると表示すべきなのかという点では、ちょっとスッキリしませんでした。
スッキリしない原因の根本は、委員会のサイトで記載されている内容と違う数値を入れるにあたっての表現の難しさです。
今言われている侵襲的検査のリスクは、かなり前のデータ
侵襲的検査に伴う流産のリスクについては、わが国では長らく、委員会のサイトに記載されている、羊水検査で0.3%(300人に1人)、絨毛検査で1%(100人に1人)という数字が当然のように使われてきました。しかし、これらの数字は、実は根拠が曖昧なのです。
「いや、根拠はある。」とおっしゃる方もおられるかもしれません。たしかに、この記載の元となったと思われる論文は存在するようです。
以前から、この種の検査のリスクについては皆、本当はどのくらいなんだろうという疑問や興味を持っていて、全世界で各種研究が行われてきました。
いろいろな研究論文があるのですが、国や地域単位で大規模に行われた調査というものは、そう多くは存在せず、多くは一施設や複数施設で検証されたものでした。そんな中で、羊水検査の流産リスクとして、数少ない大規模かつきちんとデザインされた比較研究の結果として示されているものから示された数値は、1986年にスウェーデンで行われた調査に基づく1%というものがありました。*1この数値は、ヨーロッパを中心に長らく使われてきました。
では、0.3%という数値はどこからきたのか?
調べてみると、米国のNICHD(National Institute of Child Health and Human Development:国立小児保健発育研究所)が後方視的調査の結果として、1976年に発表した数字がこれと同じでした。*2実に47年前のことです。
羊水検査・絨毛検査の流産リスクに関する新しい認識とは
その後、欧米を中心とした世界の臨床現場では、医療者たちは、こういった侵襲的検査には本当にそれだけのリスクを伴うのか? という疑問を抱きつつ検査を行ってきました。もっと新しい、現実に即した数字をもって、妊婦や家族への説明に臨むべきという考えが常にあったのです。そしていくつかの調査研究が推し進められた結果、今ではこれらの侵襲的検査に伴うリスクは、以前言われていたほど心配なものではないという結論に達しているのです。
たとえば米国で今使用されている数字は、2006年に発表された、FASTER trialという研究の結果です。*3
この研究では、30000人以上の妊婦を調査しました。そのうちの3000人ちょっとが羊水検査を受けた人たちでした。この結果、羊水検査関連の流産率は、0.06%(1600人に1人)という結果が得られています。絨毛検査については、ここまで大規模かつ条件を統一した調査はできていないのですが、経験を積むほどリスクが下がることが判明しており、数多く行っている施設では、そのリスクは羊水検査と変わらないとされています。
わたしが会員になっている、ISUOG(国際産科婦人科超音波学会)の会誌でも、侵襲的検査のリスクに関する調査の論文は、いくつも発表されてきました。
2015年に英国のグループが発表したシステマティック・レビューとメタアナリシスの論文*4では、羊水検査による流産が起こる率は0.11%、絨毛検査では0.22%という結果でした。この結果に、この後に発表された大規模調査を追加して、国際的なチームとして新たな解析を行った結果が2019年に発表されました。*5
その結論として、羊水検査や絨毛検査によって起こる流産率は、これまで妊婦に説明されてきたよりも低いとし、全く同じリスク因子を持つもの同士という条件で比較した場合、そのリスクは無視できるぐらいであると述べています。
この結論に至る根拠として記載されている具体的数値としては、羊水検査を行うことによって起こる流産リスクは、0.12%(95%信頼区間 -0.05〜0.30%)で、絨毛検査のそれは-0,11%(95%信頼区間 -0.29〜0.08%)でした。ここで、95%信頼区間が0を跨いでいるということは、検査を受けた人が流産する率と検査を受けていない人が流産する率との間に有意差がないということを示しています。
というわけで、最新の信頼性が高い大規模調査を元にした研究論文からは、これらの侵襲的検査によって、流産が増加すると心配する必要はないという結論に達することができるのです。
こういった論文は、ちょっと検索すれば誰でも入手することが可能です。日本の産婦人科医でISUOGの会員になっている人は何人もいるし、その気になればすぐに手に入る情報です。
ところが、残念なことに日本の妊婦診療の現場では、いまだにこれらの検査について、リスクを強調するような説明が行われていて、妊婦さんたちは検査の危険性に怯えています。末端の産婦人科医に国際学会における情報が行き届いていないという問題はあると思いますが、それどころか、この国を代表する委員会のような機関がオフィシャルなサイトに載せる情報からして、情報がアップデートされていないというのは大きな問題で、これをなんとかしなければなりません。
日本産科婦人科学会も見直しをはじめている
昨年、日本産科婦人科学会と日本産婦人科医会が共同事業として行っている「産婦人科診療ガイドライン」の「産科編2023」(2023年8月発刊予定)作成の段階での、パブリックコメント募集があり、新しく記載される内容案が公表されていました。
日本産科婦人科学会誌74巻11号(2022年11月)に掲載された案の中に、羊水検査・絨毛検査の流産リスクについての記載があり、ここでは「流産リスクは羊水穿刺では0.1〜0.3%、絨毛採取では0.2%上昇するとされる」とされていました。
私は、このあたりの記載について、それまでの羊水0.3%、絨毛1%一辺倒だった状態の見直しが行われたことは評価できると思いましたが、最新かつ信頼度の高い論文からの情報が反映されていないことをパブリックコメントで指摘しました(が、却下されました)。これらの記載の根拠論文は、二つあって、一つはACOG(米国産婦人科医会)のPractice Bulletin No.162(2016年)、もう一つは、先述した2015年のISUOGに掲載された論文でした。
実は先述した「妊娠中の検査に関する情報サイト」を取りまとめるにあたって、私はこのリスクの記載を改めるべきだと主張しました。
当初は、委員会の公式サイトに使用されている表(羊水検査0.3%、絨毛検査1%の記載)をそのまま使った原稿がありました。しかし、「産婦人科診療ガイドライン」の記載が変わる情報をお伝えし、少なくともこれに合わせて変更することが望ましいのではないかと意見したのです。
この情報サイトの作成も、厚生労働省が関係する事業でしたので、委員会のサイト記載との内容のずれが問題にはなりましたが、日本産科婦人科学会のガイドラインの記載が更新されるという情報にも強みがあり、流産リスクの記載は、このガイドラインに掲載される予定のものと足並みを揃えることになりました。
本当は私としては、このガイドライン記載で採用されているISUOG論文(2015年)が、2019年にアップデートされているので、最新のものを採用すべきと思っていたのですが、この意見は通りませんでした。代替案として、いろいろな報告があって数値には微妙に違いがあるので、「流産リスクはこれまで考えられていたほど高いものではない」などの表現にする案も提案しましたが、あまり安全性を強調するような書き方にはしてほしくないという意見に譲歩することになりました。
アップデートが進まないわが国の現状
このように、一部では遅々とした歩みながらもアップデートの動きはないわけではないのです。しかし、なかなか変わらないと感じざるを得ないのは何が問題なのでしょうか。
ここからは、私が長年この分野でさまざまな問題に向き合ってきた立場から持つ印象、個人的な感想になりますが、やはり根本にあるのは、なるべく検査が普及してほしくないという気持ちを持っている人の意見が反映されやすい現状ではないかと思うのです。
そもそも、主に染色体異常を見つけるための検査がどのように発展してきたかというと、羊水検査が子宮に針を穿刺するという侵襲を伴うので、できるだけこの検査を行うべき人を無侵襲的検査を用いて振り分けようという考えだったはずです。この振り分けの精度、検出感度を上げるとともに偽陽性率を下げるということが、より良いスクリーニング検査です。歴史的流れとしては、このスクリーニング検査と確定的侵襲検査との関係性の中で、どのような検査選択をすべきかが考えられてきたわけです。
検査を受ける側としては、リスクは避けたい、なるべくなら侵襲は避けて楽に検査を受けたい、しかしより確実な結果を得たい。検査を行う側に立てば、少ない労力で、特別な技術を必要とせず、失敗の少ない検査をしたい。
リスクが低いということが判明した今なら、確実な結果が得られる方法を選択するなら、羊水検査・絨毛検査がベストでしょう。しかし、これらの検査には侵襲があることは確かだし、検査を行う人の熟練度によっても安全性に差が出そう、実際にどこで受けるのがより良いか分かりにくいし、アクセスも良くない。となれば、血液検査でかなり精度が良く、かつ安価ならばこれを選んだ方が良いだろう。という考えに基づいて選択が可能になります。血液を検査施設に送って、オートメーションで解析すれば、たくさんの人の検査を同時進行できるということも血液検査のメリットの一つですね。こういった感じで、世界ではこれらの検査が普及していきました。
しかし、日本の事情は少し違います。このブログでも何度も取り上げていますが、日本では、出生前検査は長い間かなり抑制的に扱われてきました。出生前検査の存在をなるべく知らしめない、検査を受けるまでの間になんらかのハードルを設ける、検査を受けるということ自体が良くないことのようなイメージづくりをする、というようなことが行われてきました。「染色体異常があることを理由に中絶してほしくない」という考えを持つ人たちの意見が強く反映された結果だと思われます。妊娠中絶は悪いこと、というイメージが、かなり定着していることも関係しているでしょう。
「染色体異常があることを理由に中絶してほしくない」という気持ちは理解できるのですが、中絶を選択する人が多く存在することも事実で、その背景を考えつつ、どのようにしていけばより良い社会になるのかを考えなければならないと思います。
染色体異常があったとしても、産み育てることに希望を持てるように世の中が変わっていけば、中絶してほしくないという気持ちに対して、良い方向に作用するはずだと思うので、そのように変えていけるようなアクションが必要なのですが、「妊娠初期に検査をしなければ、染色体異常が発見されることはないか、発見されても中絶のできない時期になるから、検査を規制すれば良い」という形のアクションは、方向性として正しくないと思うのです。
(後編に続く)
*1 Tabor A, et al.: Randomised controlled trial of genetic amniocentesis in 4606 low risk women. Lancet 1986 Jun 7; 1(8493): 1287-93.
*2 The NICHD National Registry for Amniocentesis Study Group: Midtrimester amniocentesis for prenatal diagnosis. Safety and accuracy. JAMA 1976; 236(13): 1471-1476
*3 Eddleman KA, et al.: Pregnancy loss rates after midtrimester amniocentesis. Obstet Gynecol 2006; 108: 1067-1072
*4 Akolekar R, et al.: Procedure-related risk of miscarriage following amniocentesis and chorionic villus sampling: a systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2015; 45: 16-26
*5 Salomon LJ, et al.: Risk of miscarriage following amniocentesis or chorionic villus sampling: systematic review of literature and updated meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2019; 54: 442-451